「数学って社会に出たあと、本当に役に立つの?」
「数学って何のために学ぶんだろう?」
こんなふうに思っている人に向けて、社会人の僕から見た、数学を学ぶ価値を解説します。
結論として、数学は社会に出た後も役に立ちます。
というか、僕はおそらく全科目の中でも特に数学が一番役に立っていると思います。
今回は、その理由を解説していきます。
この記事からわかること
- 数学を学ぶ価値がわかる
- 社会に出たあと、どのように役立つかがわかる
では、さっそく内容を見ていきましょう。
数学を学ぶメリット
①論理的な思考力が身につく
数学を学ぶと、ビジネスマンの必須スキルである論理的な思考力が磨かれます。
論理的思考力というと難しく感じますが、これは要するに、「ゴール」を設定して、そのゴールに向けて考えていくっていうだけです。
ビジネスの場面でも、仕事ができる人は、最初に仕事のゴールを徹底して考えます。
そこで、その仕事の本質を的確にとらえることができれば、ミスも減りますし最小限の仕事量で最大限の成果を生むことができるわけです。
これは、ビジネスにおける最重要スキルといってもいいぐらい重要なスキルです。
なぜ、数学を学ぶとこの論理的な思考力が磨かれるのかというと、難しい数学の問題になればなるほど、解く際にはまず問題のゴールを徹底的に考える必要があります。
問題は何を聞いているのか、結局、どうなったら問題を「解いた」ことになるのか、どういう条件を満たせば「解いた」ことになるのか。
また、問題のゴールを因数分解し、各要素について考察を加えていきます。
これはまさに、論理的に思考しているということです。なので、これを続けているうちに論理的な思考力が磨かれていくわけです。
②定量化の技術が備わる
先ほどの論理的な思考と関連しますが、人が何か達成するときは、明確な「ゴール」が必要です。
そして、そのゴールは定量的である必要があります。
定量的というのは、数字で表すことができるということです。
「ゴール」は、誰が見ても解釈のズレが起こらないくらい「完全に」明確にしなければいけません。
そこで、この「ゴール」を定量化する必要があるわけです。
当たり前の話ですが、数学では求められる「解」がほとんどの場合、定量的です。
数学的な力が磨かれるほど、「ゴール」を定量的に定める習慣が身に付きます。
ゆえに、論理的に「ゴール」に近づいていくことができ、結果的に最短で目標を達成することができます。
③全体観が磨かれる
数学の偏差値が60を超えているような人であれば、わかる人がいるかもしれませんが、数学の力がついてくると、問題を見た瞬間におおよその「解の形」が感覚的にわかるようになります。
たとえば、「この回転体の体積を答えよ」みたいな問題であれば、「体積はおおよそこれくらいの値になって、そこまでの道筋はだいたいこんな感じかな」みたいに直感的にわかることがあるんですね。
そして、このような全体像がパッと見えるという能力はとても高度な能力です。
論理的な思考能力が「直感」に昇華するわけです。
このような能力を、世間的には「メタ認知」と呼んでいます。
そして、ずば抜けて仕事ができる人というのは、やはりこのメタ認知能力が総じて高いですね。
僕が尊敬している職場の先輩は口癖のように、「全体観をもって仕事をしなければ、仕事はなかなかうまくはいかない」といつも言っています。
全体観をもって仕事をするというのは、要するに、細部だけを見ずに全体を見るということです。
仕事は進めていると、つい、大きなゴールが細分化された細かい一つ一つの問題を必死に解いていることが良くあります。
しかし、往々にして部分最適解を多少犠牲にしても、全体最適解を優先した方がいいことはよくあります。
数学を学ぶことで、この「全体」を鳥の目のように見る目を養うことができます。
まとめ
以上の内容をまとめていきます。
社会人視点で、数学を学ぶメリットは以下の3つが考えられます。
- 論理的な思考力が身につく
- 定量化の技術が備わる
- 全体観が磨かれる
社会人の僕から見ても数学を学ぶ価値は十分にありますので、今、数学の勉強を頑張っている方はこれをモチベーションにしてしっかり学んでいってください。以上。
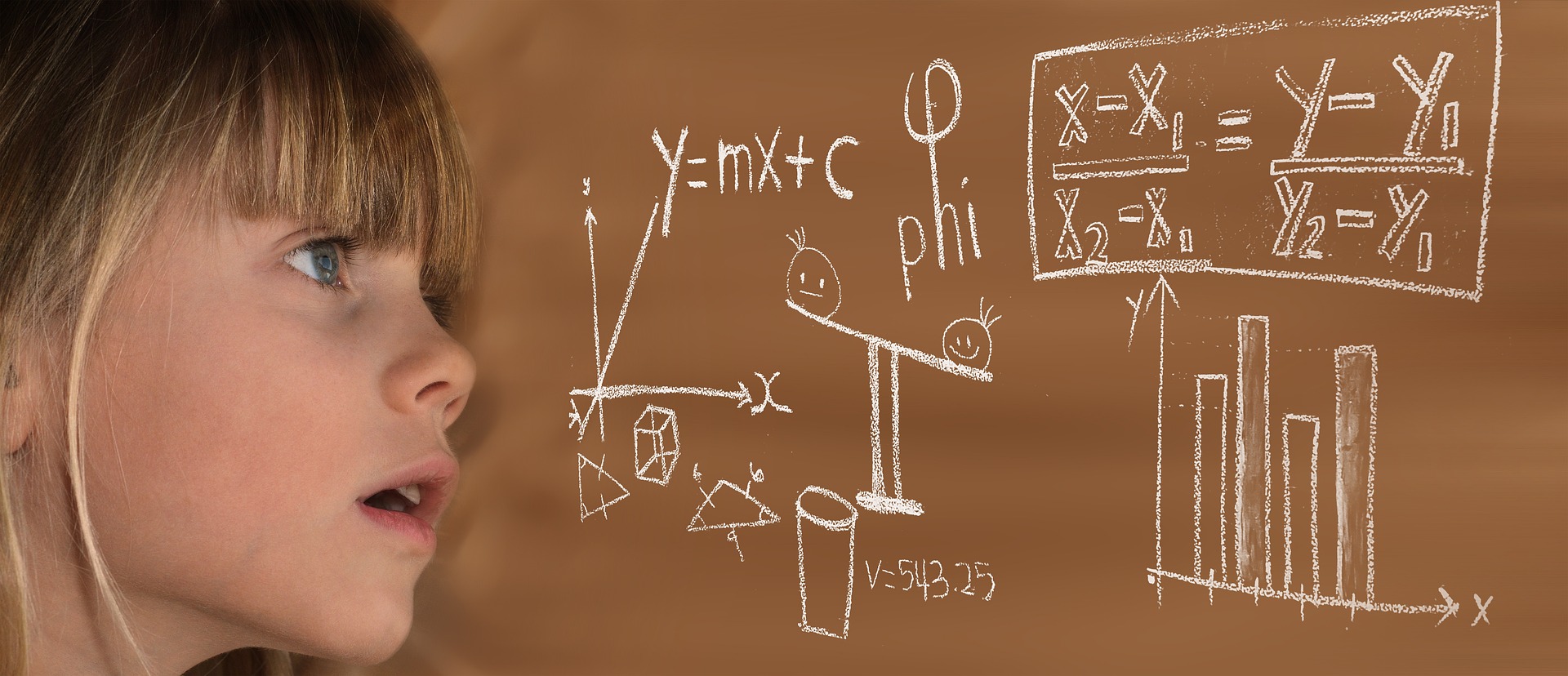


コメント